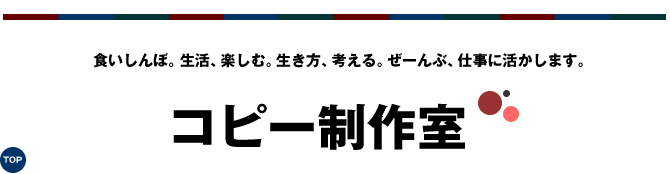シーサーが招く夏。

わが家のバルコニーには、ぎょろりと目をむいたシーサーがいる。
数年前の夏、沖縄を旅したときに出会って、一目惚れしたシーサーだ。
珍しく何度か雪化粧をした昨冬は、シーサーも白い雪をかぶり、
いっそう目を白黒させているように見えた。
春から初夏、そして日に日に日ざしが夏めくと
出番だとばかり存在感を増していく。
いや、本当はシーサーの表情は変わるはずはない。
見る者の心がそう見てしまうのだ。
そして、シーサーの先には、濃密な青の空と海に
真っ赤なハイビスカスやデイゴが咲く沖縄の風景が浮かぶ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
初めて沖縄を旅した人には、ほら、あそこにも、ここにも、と
目に留まるのがシーサーだろう。
土産物屋などの店先にはもちろんだが、民家の屋根や門柱、庭先に
置かれて、ちゃんと沖縄の暮らしと共にある。
沖縄にはもともとムンヌキムン(悪魔をよける物)と呼ばれる
さまざまな魔除けがあるという。
その代表がシーサーなのだそう。
シーサーを見ると、私たちが子どもの頃から見慣れた
寺社の参道にある狛犬を連想する。
どちらもルーツは、古代のオリエント文明にさかのぼるそうだ。
今の中東、イラクやシリア辺りに栄えたメソポタミア社会では、
王は勇気の証明としてライオン狩りを行った。
ライオンは強い力を象徴する聖獣として、シルクロードを東へと伝わり、
唐の時代の中国では唐獅子となり、
当時の日本へ、そして琉球王朝の栄える沖縄へと広まった。
シルクロードの終点、日本の本土にあっては獅子が転じて犬になり、
沖縄ではシーサーになったというわけだ。
・ ・ ・
とはいえ、民家の赤瓦屋根にシーサーが見られるようになったのは、
明治時代になって琉球から沖縄県となり、
屋根の瓦葺きが庶民にも許可されてからのことだという。
度重なる台風や飢饉、そして太平洋戦争の苦難を経て、
今家々の屋根や玄関先でカッと目を見開き、精一杯コワイ顔で
家々を守るシーサーには、そんな沖縄に暮らす人々の歴史や、
おだやかに家内安全で暮らしたいという
深い思いが込められているのだと思う。
沖縄からはるばる大阪へやって来たシーサーは、
波の音も、亜熱帯の木を揺らして渡る風の音も無縁だけれど、
魔を除け夏を呼び寄せてくれる。
シーサーが守ってくれるわが3LDK・北摂の山並みが見える住まいには、
そんな風にいつも身近に沖縄がある。
今夜はゴーヤチャンプルーとキンキンに冷たい泡盛のシークワーサー割で、
娘たちが巣立ってちょっとぎこちない2人時間を彩ってみよう。
●写真のシーサーは
若手作家の諸見里剛さんの手になる漆喰赤瓦シーサー。
沖縄ではよく見られる単体のシーサーです。
恩納村ムーンビーチ近くに工房を構える諸見里さんは、
だんだん見られなくなった沖縄民家の赤瓦を使って
独自のシーサーを作っています。
おおらかな作品には日本中にファンがいて、
東京や大阪など各地で個展が開かれます。
ぎゃらりーゆしびん(諸見里 剛さんのHP)
http://www6.ocn.ne.jp/~yushibin/
■デザイン/(株)スタジオVIS ■フォト/十時写真事務所
- ●人からパワーを
- 10/15
書を感じてください。 - 10/09
和鉄は生きている。 - 10/01
明治の夢、国産紅茶をつくる。 - ●隠れ名店を捜せ!
- 09/04
尼っ子自慢の“和の心” - 05/07
受け継がれる京銘菓 - 04/02
小さな店の極上プリン - ●森野みなみessay
- 07/01
遠足いきますか、おべんと箱 - 08/31
幸運を呼ぶガラス。 - 04/02
再び、マイお箸。 - ●マチコの好奇心一直線
- 07/01
コピ制ホームページ - 09/22
成田エクスプレス - 03/03
盆梅展

学生時代を送った神戸で39年ぶりに教養課程の中国語クラスの同窓会に参加した。いい歳こいて30分後にはみんな子供だった。